
- 現役Webマーケター
(元Webディレクター) - 東証一部上場の不動産系企業で勤務
- 最高収益:月間30万円


皆さんが日々利用しているGoogle検索ですが、これまでに数々のアップデートを行われていきたのはご存知でしょうか。
メジャーなアップデートであれば、パンダアップデートやペンギンアップデートなどが有名で一度は聞いたことがある方もいるかと思います。
今回はGoogleの検索エンジンのアップデートの歴史を学んで、SEO対策と切り離せないGoogleという検索エンジンの特徴や傾向を掴んでもらえたらと思い記事としてまとめました。

ブラックハットSEOとは、簡単に言うとGoogleやYahooなどの検索エンジンを欺いて検索結果ページの順位を操作するSEO施策を指します。以前は検索エンジンの仕組みに抜け穴があり、検索結果ページの順位を操作しやすい環境だったので検索エンジンを騙すようなSEO施策が横行していました。
近年では検索結果ページの順位決定の仕組みが高度・複雑になり、ブラックハットSEOは通用しなくなり、逆にペナルティーもらうリスクが高くなっています。今回は間違えたSEO施策を行わないように、ブラックハットSEOについて学んでいきましょう。
逆にホワイトハットSEOはブラックハットSEOの反対語にあたり、検索エンジンとユーザーの両方を考慮したSEO対策を指します。もっと詳しくいうと、検索エンジンが理想とするガイドラインに沿ってコンテンツを制作、サイトに掲載することです。またユーザーの期待を超える付加価値のある良質なコンテンツを提供することです。
・検索エンジンではなく、ユーザーの利便性を最優先に考慮してページを作成する。
品質に関するガイドライン
・ユーザーをだますようなことをしない。
・検索エンジンでの掲載位置を上げるための不正行為をしない。ランクを競っているサイトや Google 社員に対して自分が行った対策を説明するときに、やましい点がないかどうかが判断の目安です。その他にも、ユーザーにとって役立つかどうか、検索エンジンがなくても同じことをするかどうか、などのポイントを確認してみてください。
・どうすれば自分のウェブサイトが独自性や、価値、魅力のあるサイトと言えるようになるかを考えてみる。同分野の他のサイトとの差別化を図ります。
またSearch Consoleヘルプでは基本方針の記載があります。必死に検索エンジンの仕組みの抜け穴を探すのではなく、ユーザーのことを考えて価値・魅力のあるコンテンツ作りをしましょうということですね。
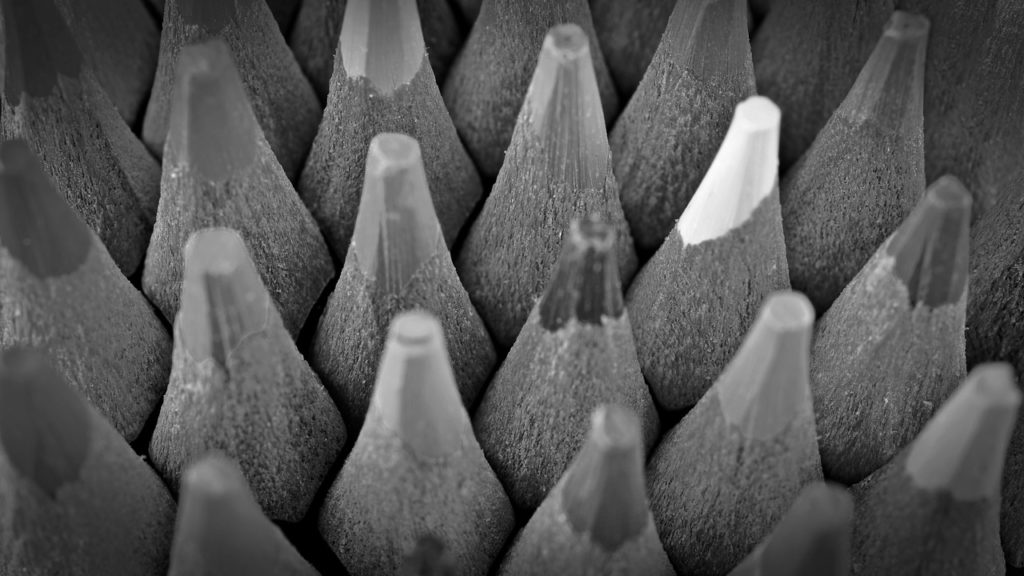
ここではブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違いについて説明していきたいと思います。
ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの明確な違いとしては、Googleも言っているように、ユーザーに価値・魅力を与える施策であるかどうかという点です。
ブラックハットSEOは検索エンジン、ユーザーからの評価は関係なく、検索結果ページに上位表示させるための手法であり、Googleの基本方針から逸脱しています。
良質なコンテンツは自然とユーザーから評価を受けて、そのシグナルを元にGoogle検索結果ページで上位に表示されるという前提を忘れずに心がけましょう。
と言っても指標がないと判断がつかないこともあると思います。
Googleはそんな Web担当者の方、Webサイトの所有者向けにガイドラインを設けているのでSerach Consoleのヘルプから閲覧できるウェブマスター向けガイドライン、品質に関するガイドラインなどを参考にしてSEO施策に取り組めば問題ありません。

リンク売買はお金を払って被リンクを獲得することを指します。お金を払って外部サイトから、PageRankがほしいページに対して、リンクを付けることを指します。
Googleは本来被リンクは意図的に集めるものではなく、良質なコンテンツに自然に集まることがあるべき姿と考えています。
相互リンクすることが自体が目的であったり、特定のサイトから過度にリンクを付け合うことを指します。
リンクすることが目的ではなく、ユーザーに価値のある深い情報を伝えるためリンクするようにしましょう。
ワードサラダとは、プログラムを使って自動的にコンテンツを作ることを指します。
サイトやページに合ったキーワードは入っているが文脈として正しくなかったり、意味をなさないコンテンツを作ることになります。
キーワードスタッフィングはタイトルや見出しなどにキーワードを詰め込むことを指します。
キーワードを詰め込み過ぎて、日本語の文脈として正しくなかったり、意味をなさないコンテンツを作ることです。
第三者が作成したコンテンツのソースコードをコピペして、インターネット上に重複コンテンツを作ることです。
ユーザーからは見えない部分、見えにくい部分にテキストやリンクを配置することです。
ユーザーからは見えないようにして、検索エンジンのみが大量のテキスト・リンクがあるように誤認させることを指します。
具体的には、文字サイズを極限まで小さくしたり、白背景の箇所でフォントカラーに白を使うなどがあります。
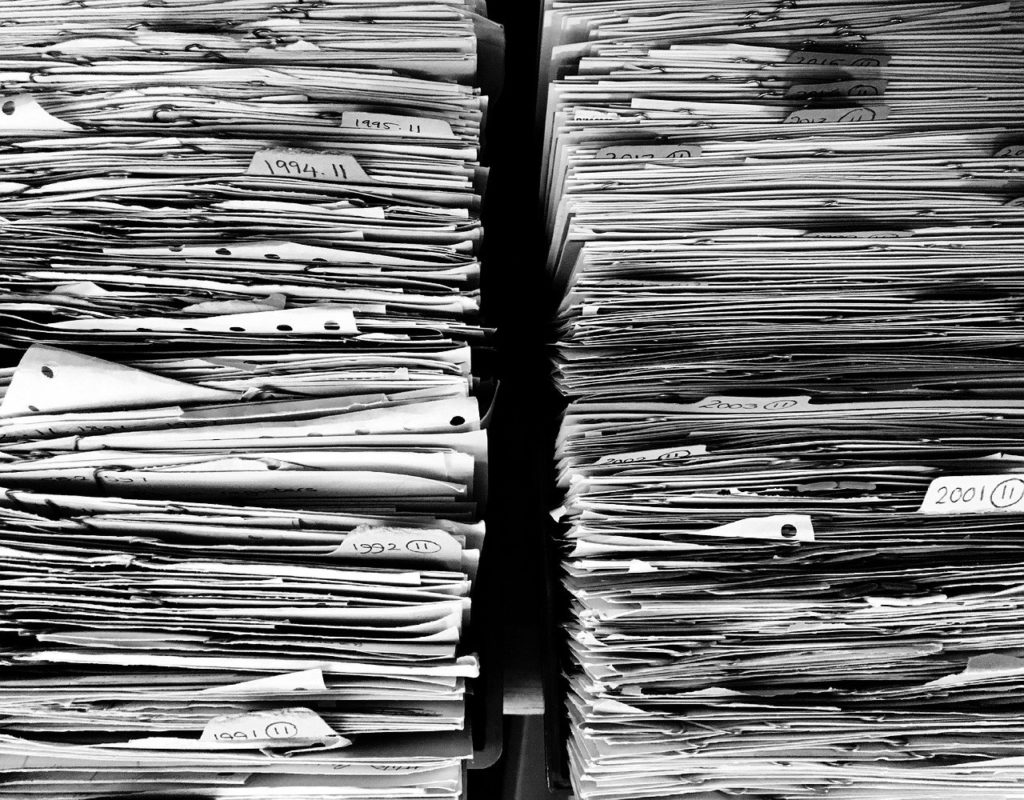
カフェインアップデートは2010年6月8日に実施されたGoogle検索エンジンのインデックス・システムの改善を目的としたアップデートです。今では当たり前のように新しくWebサイトを新規で構築すれば、いずれGooglebotがクロールしてインデックスされていますが、カフェインアップデートにより新たなWebサイトのインデックススピード・量が改善されました。
カフェインを使用すると、非常に大きな規模でWebページのインデックスを作成できます。実際、Caffeineは毎秒数十万ページを並行して処理します。これが紙の山だった場合、毎秒3マイル伸びます。カフェインは1つのデータベースで1億ギガバイト近くのストレージを占め、1日あたり数十万ギガバイトの割合で新しい情報を追加します。
新しい検索インデックス:カフェイン
上から下に段階的にインデックスするのではなく、縦横無尽にグローバルに新しいページ・既存ページの更新を検知しインデックスすることで、より新鮮な情報を早く検索結果に表示することができるようになりました。
ハミングバードアップデートは2013年9月に実施された会話型検索を行うためのアップデートです。
例えば、「大阪駅に近いラーメン屋」とユーザーが入力した場合、その検索クエリ「大阪駅」「近い」「ラーメン屋」という検索クエリを含んでいるかどうかだけでコンテンツが表示されていました。
しかし、ハミングバードアップデートによって、文脈から「大阪駅から物理的に近いラーメン屋を検索したいのだろう」と検索エンジンがユーザーの検索クエリから検索意図を汲み取って、検索結果を表示してくれるようになりました。
パイレーツアップデートは2012年8月から実施されたデジタルミレニアム法案(DMCA)を基準として、著作権を侵害したWebサイトを検索結果ページの上位に表示させないようにするアップデートです。直近では2014年に更新されています。
2014年12月に実施されたユーザーの位置情報を元に最適な検索結果を表示するアップデートです。
例えば、「ラーメン」「居酒屋」と検索すると、ユーザーの位置情報から近くのエリアのお店が表示されるようになりました。より地域性が重視な検索クエリに対して、関連性の高いWebサイトが上位に表示されるように改善されました。
自分が大阪にいる時に東京駅付近の「ラーメン」「居酒屋」のお店が表示されても困りますよね。
ユーザーは今自分がいる場所を基準に近くのお店を探しているのだろうと検索エンジンが解釈して検索結果が表示されるようになったというわけです。
パンダアップデートは2011年2月に実施された他のWebサイトのコピーコンテンツやちょっとリライトしただけのページなど、いわゆるオリジナリティーの無いコンテンツを掲載しているWebサイトの検索順位を下げるまたは検索結果ページから削除するアップデートです。実際に日本語検索エンジンにも反映されたのは2012年7月です。
もちろん低品質なWebサイトの検索順位が下がったり、削除されるので相対的に高品質なコンテンツを提供しているWebサイトの検索順位が上がるようになりました。
Googleウェブマスター向け公式ブログの「良質なサイトを作るためのアドバイス」ではWebサイトで良質なコンテンツを作るための25のチェックポイントが掲載されています。
独自のコンテンツであるか、信頼できる情報であるかなど、今後の検索エンジンのアップデートのテーマでもあるWebサイトに掲載されている情報の魅力や信憑性に対してGoogleが意識していることが分かりますね。
ペンギンアップデートは2012年4月に実施されたリンク売買・過度な相互リンクなどブラックハットSEOと呼ばれるリンクスパムなどを行なっているWebサイトの検索順位を下げるアップデートです。最悪の場合、Googleからペナルティーを受けて、検索結果ページから削除されるケースもありました。
最も直近の2016年9月23日のペンギンアップデート4.0はリアルタイムに反映されるように改善されています。また現在ではペンギンアップデートはコアアルゴリズムに含まれています。
ペンギンアップデートは今後も実施している方針であり、Webサイトの担当者や自身のWebサイトを運営されている方はホワイトハットSEOを行うように心がけなければなりません。
Rank Brainは2015年10月26日に実施された機械学習を取り入れたアップデートです。ユーザーが入力した検索クエリとインターネット上のコンテンツの関連性をAIが分析する検索アルゴリズムです。
検索結果ページの順位を決定するランキング要素は2000以上あると言われていますが、その中でRank Brainは3番目に重要なランキング要素とされています。
具体的には「ここから近いラーメン屋さんはどこ?」と検索した場合、「どこの場所を基準にして近いのか」を検索アルゴリズムが分析を行なった上で検索結果を表示してくれます。
クオリティアップデートは2015年5月7日に実施されたコンテンツの品質に関するアップデートです。似たようアップデートにパンダアップデートがあるのですが、大きな違いとしては、そのアルゴリズム変更の影響範囲です。
パンダアップデートはWebサイト・ページ単位での順位変動でしたが、クオリティアップデートは検索エンジンの根幹のアルゴリズムの変更になるため、全てのWebサイトに影響がありました。
モバイルフレンドリーアップデートは2015年4月21日に実施されたスマホ対応できていないWebサイトの評価が下がるアップデートです。スマホの普及に伴い、ユーザーのスマホでのインターネット検索を考慮したアップデートになります。
インタースティシャルアップデートは2015年11月1日に実施されたWebサイトにアクセスした際に、画面全体に広告表示をしているWebサイトの評価を下げるアップデートです。
Googleはユーザーにより良いコンテンツ、体験を提供することを重視しているため、不快に感じる広告に関しては嫌う傾向があります。
日本語検索アップデートは2017年2月3日に実施された世界的に見ても異例のアップデートで、日本語の検索エンジンのみが対象のアップデートです。医療に関する低品質なWebサイトの検索順位を下げる改善が行われました。
このアップデートの背景としては、医療に関する低品質なコンテンツを提供しているキュレーションサイトが増加したことにあります。
医療は人間の生命に関わる内容が多いと思いますが、医学的に根拠が無かったり、内容に誤りがあるなど低品質なコンテンツで溢れかえっていました。
そこでGoogleは日本語の検索エンジンのみが対象にアップデートを実施しました。
健康アルゴリズムアップデートは先程の日本語検索アップデートと同じく、日本語の検索エンジンのみが対象のアップデートです。2017年12月6日に実施されました。
名前の通り、医療や健康といったジャンルのWebサイトで根拠が無かったり、内容に誤りがある低品質なコンテンツを提供しているWebサイト、また医療や健康のジャンルを取り扱う上で信頼できないWebサイトの順位変動がありました。
YYML(Your Money or Your Life)はお金や人の生活に関わるジャンルを扱っているWebサイトが対象でした。もっと詳しくいうと、将来の幸福、健康、お金などコンテンツの品質が重要なジャンルのため情報の信憑性が問われます。
コアアルゴリズムアップデートは年に数回実施される検索エンジンのアルゴリズムの根幹を見直すアップデートです。2019年には3月12日、6月4日、9月24日の計3回行なわれており、2020年では1月と5月に実施されています。
コアアルゴリズムのアップデートは影響範囲が広いこともあってか、Googleの公式Twitterでアルゴリズムのアップデートの発表が事前に告知されています。
コアアルゴリズムアップデートは明確に何が変更されるかは発表されていません。しかし多くのWebサイトで順位変動が見られて、一時的に順位が上がったり下がることもあります。基本的には3日〜1週間程かけて順位が徐々に安定していきます。
BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)は自然言語処理技術の一つで、人間の使う言葉の意味や文脈といった今までコンピューターが理解できなかったことをコンピューターでも適切に処理できるようにしたアップデートです。2019年12月10日に日本語版を含む70カ国で実施されました。